酵素最新ニュース

店長山本は、日々少しずつ発見・解明される酵素関連ニュースを楽しみにしています!
酵素は現代化学最大の謎ですからね。
これから期待される酵素の可能性について参考にしてみてください。
【飲酒時の皮膚の紅潮は、がんリスク上昇のサイン?】
2009年03月24日付 EurekAlert
東アジア地域の多くの人々は酵素欠損症を有し、アルコールを飲んだとき皮膚が紅潮する。アメリカ国立アルコール乱用・依存症研究所と日本の久里浜アルコール症センターの共同研究チームが、そのような症状を持つ人々(世界に約8%いるようだ)が大量に飲酒すると食道がんのリスクが非常に高まると警告した。アルコールの代謝に欠かせないアルデヒド脱水素酵素2(ALDH2)には遺伝子多型があることが知られている。東アジアの人々の主要なALDH2遺伝子異型は2つあり、そのうちの1つは不活性な酵素を生産するため、アルコールで顔が赤くなるのだが、この不活性酵素の遺伝子異型をひとつもつことで食道がんのリスクが6-10倍高まるという。このタイプの遺伝子を持つヒトが一日5杯以上の飲酒を続けると、食道がんのリスクは非飲酒者の89倍に達する。
【食べても太らない体にできる酵素が発見される】
2009年03月16日 GIGAZINE
脂肪のコントロールをする役割を持つ酵素が発見され、肥満や糖尿病、心臓病などを防ぐ鍵になるのではないかと考えられているそうです。この酵素を操作すると、食べても食べても太らないという、一部の人間からは非常にうらやましがられるタイプの体になれる可能性もあるようです。
詳細は以下から。
Fat enzyme explains why some people don't get flabby - Telegraph
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/4995048/Fat-enzyme-explains-why-some-people-dont-get-flabby.html
ウエスト付近の皮膚下にエネルギーを溜め込むかどうか決定する酵素「MGAT2」を失ったマウスが、高脂肪の食事をしても体重過多にならないことが科学者によって発見されたそうです。また、MGAT2のないマウスは耐糖能異常にならず、肝細胞に脂肪がつかなかったとのこと。MGAT2はマウスと人間に共通してある酵素MGATのひとつで、薬によって行動を抑えて肥満に対処できるのではないかと考えられているそうです。
カリフォルニア大学のRobert Farese博士たちの研究では、MGAT2を操作したマウスは16週間後に通常のマウスより40%少ない体重となり、運ばれる脂肪の量は50%以上少なくなっていました。また心臓病の原因にもなる血中の有害コレステロールも減少したそうです。さらに長期間の実験で、MGAT2のないマウスはインシュリンが少なく、グルコース不耐性が良くなるという結果が出たとのこと。
現代の人間が肥満になるのは、人類が豊かな食事にありつけなかった何千年も昔のころの機能が働いているためと考えられており、MGAT酵素はエネルギー貯蔵装置としては重要な役割を担っているそうですが、食事に困らず肥満が気になる人は治療のためこの酵素の機能を停止するということがこれから行われるのかもしれません。
【「納豆酵素はアルツハイマー治療に有望」研究結果】
2009年2月24日 gooニュース
納豆とは、匂いのきついネバネバした大豆製品だ。しかし、アルツハイマー症を撃退してくれる可能性がある。
日本のテレビ番組『Iron Chef(料理の鉄人)』のテーマ食材にもなった納豆は、ナットウキナーゼという酵素を含む。ナットウキナーゼには脳のプラークを分解する作用があり、化学者たちは画期的な治療薬が生まれるかもしれないと期待している。
ナットウキナーゼは理論上、アミロイドと呼ばれる有害なタンパク質を分解してくれる。アミロイドはアルツハイマー症の患者の脳に線維性の沈着物を形成する。
「アミロイド線維を分解するナットウキナーゼの能力はかなり有望だ」と、[カリフォルニア大学サンフランシスコ校]グラッドストーン神経疾患研究所に所属するアルツハイマー症の専門家Li Gan氏は言う。「健康食品に含まれる酵素なので、副作用も少ない可能性がある」
アルツハイマー症は500万人以上を苦しめる変性疾患で、治療法は確立されていない。中度の記憶障害を少し和らげる薬はいくつかあるが、病気をさらに理解し、治療のための新たな対策を作ることが求められている。
国立台湾大学の化学者Rita Chen氏のチームも、ナットウキナーゼが3種類の有害なタンパク質の線維を分解できることを明らかにしている。『Journal of Agricultural and Food Chemistry』誌に掲載された論文の中で、試験用の薬は経口摂取すれば体の各部に届けられるが、脳には届かないかもしれないと述べている。アルツハイマー症の患者は脳に作用する薬を必要としている。
それでも、もしナットウキナーゼを脳で作用させることができれば、ただの対症療法ではなくダメージを修復する方法がついに得られる可能性がある。ただし、タンパク質の線維を分解すると、状況がさらに悪くなる危険もある。
「線維を分解することは必ずしも有益とは限らない」とGan氏は指摘する。「例えば、粉々にされた線維が線維性ではなくなり、集合すれば、かえって有害になる可能性もある」
[アルツハイマー型認知症は、病理学的には脳組織の萎縮のほか、大脳皮質の老人斑の出現がみられ、老人斑はβアミロイドの沈着であることが明らかになっている。ただし、このβアミロイドが本症の直接原因なのか、それとも結果であるのかについて結論は得られていない]
Gan氏もChen氏も、次の研究プロセスは、ナットウキナーゼを動物に与えて実験することだと同意している。Chen氏は、納豆を大量に食べる人がアルツハイマー症のリスクが低いかどうか疫学的な調査も可能だとしている。
ナットウキナーゼがアルツハイマー症の強力な薬になるかどうかはまだわからない。しかし納豆は、日本食品店の冷凍庫でいつでも買うことができる。ご飯や寿司、豚肉と一緒に供されることが多いこの見慣れない食べ物を試してみるのもいいかもしれない。
【万田酵素が「新しい顔」でテスト販売を実施】
2008年11月27日 美容健康EXPO
万田(株)(本社広島県三原市、松浦良紀社長)は、健康補助食品「万田酵素」のパッケージデザインなどを変更した商品を「爽」として、テスト販売。同製品の若年層への訴求などを目的とし、ダイエー薬品部108店舗などでテスト販売している。万田酵素爽のテストマーケティングは、今年いっぱいまで実施される。
同社でも初の試みとなる、万田酵素のテストマーケティングは、50代以上の層に対し、強い知名度を誇る同製品のさらなる拡販を目指し、今秋よりスタート。より若い層への訴求を目指し、従来のイメージをガラリと変えたパッケージ、分包の採用など、万田酵素の「新しい顔」が打ち出されている。
「これまで万田酵素は特に50代以上に対し、よく理解していただき、知名度もあると自負しております。しかし、一方で、F1後半からF2前半の若い層がファスティングダイエットなどで酵素について徐々に認知され始めている中で、そういった年齢層へ十分に訴求できていない部分もあります。そこで価格やデザインを一新した商品をテスト販売、という形でマーケティングを実施することになりました」(同社マーケティング室・伊藤伸夫氏)。
新パッケージの「万田酵素爽」は、ライトなデザイン。ペーストも分包となっており、使いやすく、携帯にも便利な仕様となっている。
万田酵素は、味噌や醤油で知られる発酵食品の一種だが、53種類以上の植物素材を発酵させており、その製造には熟練した技術と経験が必要とされる。自然の恵みを凝縮した「万田酵素」にはさまざまな健康効果が期待され、多くの研究報告もなされている。
同社では、今回のテストマーケティングを2008年いっぱいまで続け、売れ行きや同梱したアンケートなどの結果をみながら、本発売を検討する。税込の価格は、2,980円(14包入り)。
【新酵素:石油を使わないバイオ素材に光 福井県立大・濱野講師ら発見 /北陸】
2008年11月14日付 毎日新聞 地方版
◇米科学誌電子版に掲載
土壌にいる放線菌が作りだし、天然の食品保存料として使用される「ポリリジン」を合成する酵素を、福井県立大の濱野吉十(よしみつ)講師と、化学会社「チッソ」横浜研究所のグループが発見した。ポリリジンはアミノ酸の「リジン」が数十個鎖状につながった構造でナイロンなどと構造が似ており、酵素の遺伝子を改良すれば石油を原料としない強固なバイオプラスチックが作れるという。研究成果は10日付の米科学誌「ネイチャー・ケミカルバイオロジー」電子版に掲載された。
濱野講師は「でんぷんや糖を原料にしたバイオプラスチックはあるが、合成方法が非効率的のうえ、強度に欠ける。アミノ酸を原料に今回発見した酵素を用いれば、強じんで油や薬剤に耐性があるバイオプラスチックが作り出せる」と話している。(菅沼舞)
【県立大講師ら合成酵素を発見 新素材への応用に期待】
2008年11月11日付 中日新聞
微生物が作る天然のアミノ酸の一種「ポリリジン」を合成する酵素を、県立大の浜野吉十(よしみつ)講師(応用微生物学)とチッソ横浜研究所の共同研究グループが世界で初めて発見した。ポリリジンはナイロンと似た構造を持っているため、今後、石油を使わないバイオプラスチックへの応用も期待される。10日付の米科学誌「ネイチャー・ケミカル・バイオロジー」電子版に掲載された。
ポリリジンは、土壌の中にいる放線菌という微生物が作り出し、抗菌性があり、数少ない天然の保存料として利用されているが、合成されるメカニズムは長年解明されていなかった。浜野講師らは2005年4月から研究を開始。チッソの特殊技術を駆使し、放線菌からポリリジンを合成する酵素を取り出すことに成功した。酵素の遺伝子を解析し、ポリリジンが以前から知られていた酵素とは異なる、新たな酵素によって作られていることを突き止めた。
また、このポリリジンの合成酵素を応用して、新たなアミノ酸を作ることにも成功。この酵素の改良を重ねることで、ナイロンのようにすぐれた耐性を持つバイオプラスチックなどの新素材を微生物から生産できる可能性も秘めており、化石燃料依存脱却の“救世主”として注目される。 (増田紗苗)
【生物原料から高強度プラスチック、関与の「酵素」発見】
2008年11月11日00時03分付 読売新聞
生物を構成するたんぱく質の原料となるアミノ酸を使って、高強度で柔軟なプラスチックを作り出せる酵素を福井県立大学とチッソ(本社・東京)の研究チームが放線菌から発見した。
10日付の科学誌ネイチャー・ケミカルバイオロジーに発表した。
これまで、放線菌がアミノ酸の一種「リジン」がつながった「ポリリジン」を作り出すことは知られていた。研究チームは、生体の反応を促進する「酵素」がこれに関係していると考え、菌が作り出す数万に及ぶ酵素の中から、リジンを接着剤のように一気につなぐものを見つけた。酵素の一部を変えれば、リジン以外のアミノ酸にも応用可能という。
【がんのリスク・マネジメント:(15)野菜・果物とがん:期待される予防効果】
2008年11月4日付 毎日jp 毎日らいふ
色彩鮮やかな野菜や果物は、ビタミンやミネラルが豊富で、体の調子を整える食品としての健康的なイメージが定着しています。その成分には、がん予防にも有用と思われる機能が知られているものがあります。
例えば、緑黄色野菜に多く含まれるカロテン、柑橘系果物に豊富なビタミンC、トマトに含まれるリコピンなどは、生体内で発生した活性酸素を消去する抗酸化作用があります。
キャベツやブロッコリーなどのアブラナ科野菜に多く含まれるイソチオシアネートは、体内で発がん物質を解毒する酵素の活性を高める作用があることが知られています。
ほうれん草など緑葉の野菜や果物に多く含まれる葉酸は、DNAの合成に欠かせない成分です。にんにくやタマネギなどのアリウム野菜中のいくつかの成分には、抗酸化作用や発がん物質の生成抑制・解毒促進などの作用があることが知られています。
そうはいっても、がんについては、今日、明日の食事内容が将来の予防に直接結びつくというわけではありませんが、普段から野菜や果物をよく食べている人で、いくつかの、主に上部消化管のがんの予防効果が期待できるという疫学研究からのエビデンスも沢山あります。
世界がん研究基金(WCRF)と米国がん研究協会(AICR)による「食事、栄養、身体活動とがん予防の世界評価」の2007年の改訂では、果物については、口腔・咽頭・喉頭、食道、胃、肺のがんに対して、また、野菜(穀類やいも類など、でんぷん質のものを除く)については、口腔・咽頭・喉頭、食道、胃のがんに対してリスクを下げる可能性大と評価されています。
さらにアリウム野菜(胃)、食物繊維(大腸)、にんにく(大腸)、葉酸(膵臓)、カロテノイド(口腔・咽頭・喉頭、肺)、β-カロテン(食道)、ビタミンC(食道)、リコピン(前立腺)についても、可能性大と判定しています。
このように、世界的な機関によるエビデンスの総合評価において、単一の食品や栄養素にまで踏み込んで判定されたのは、がん予防では初めてのことです。大勢の人に一斉に行うアンケート調査から、誰が何の食品をどれくらい摂っているのかという正確なデータを得るのは大変難しいのですが、単一の食品や栄養素について、病気のリスクを分析できるような新しい研究が普及し、ようやくデータが揃ってきたのです。
なお、以上はすべて食事から摂った場合です。サプリメントとして摂った場合の評価は別扱いになっていますので、次回に紹介します。
ひるがえって、多目的コホート研究では、野菜や果物が不足しているグループで胃がんリスクが高いことが示されました。とはいえ、多く食べれば食べるほど予防効果があるというような関係ではありませんでした。
日本人男性に多い食道の扁平上皮がんについては、野菜・果物の摂取量が、1日当たり100g多くなるごとに、11%ずつリスクが下がるというクリアな関係が見られました。この効果は喫煙・大量飲酒者ではさらに大きかったのですが、もともとたばこも吸わずお酒も飲まなければ、このタイプの食道がんになる人はあまりいませんので、やはり禁煙と節酒が先決です。
一方、大腸がんや肺がんについては、野菜・果物の量は影響していませんでした。さらに、がん全体との関連について調べましたが、野菜・果物のいずれも予防効果は認められませんでした。ただし、果物については、脳卒中・心筋梗塞などの循環器系疾患に対する予防効果が認められました。(津金 昌一郎)
【神経芽腫:原因特定 肺がん遺伝子と同じ、治療薬に道】
毎日新聞 2008年10月16日付 東京朝刊
小児がんの一種「神経芽腫(がしゅ)」の原因遺伝子の一つを、小川誠司・東京大特任准教授(腫瘍(しゅよう)学)らが特定した。肺がんなどの原因遺伝子としても知られ、欧米で開発中の薬剤が効果的な治療薬になる可能性がある。16日付の英科学誌ネイチャーで発表した。
研究チームは、遺伝子の異常を高精度に検出する技術を開発し、神経芽腫の細胞を調べた。その結果、細胞増殖を担う酵素をつくる遺伝子「ALK」の働きが異常に活発化していることが分かった。
患者215人のALKを調べると、18人(8・4%)で遺伝子の働きが活発化していた。うち、難治性の進行性がん患者80人に限ると16人(20%)に上った。
神経芽腫は年間約1000人が発症し、小児では白血病と脳腫瘍(しゅよう)に次いで多いがん。84年に別の原因遺伝子が見つかったが、阻害薬の開発が難しかった。
小川特任准教授は「ALK阻害薬は開発が進み、早い時期に治療に使うことができるようになる。患者と家族には大きな希望になるはずだ」と話す。(関東晋慈)
【酵素がHIV増殖弱める 京大、新薬開発に期待】
2008年10月6日付 共同通信
人の細胞にあってエイズウイルス(HIV)の増殖をじゃまする「APOBEC」というタンパク質が、特定の酵素の働きでより強い防御力を得ることを、京都大の高折晃史講師らの研究チームが突き止め、米科学誌の電子版に6日発表した。
酵素は「Aキナーゼ」と呼ばれ、HIV感染した細胞に加えると増殖の勢いが弱まった。
HIV治療では、既存の薬が効かない薬剤耐性ウイルスの拡大が世界的な脅威。高折講師は「新たな治療薬の手掛かりにしたい」と話している。
APOBECはHIVの遺伝子を変異させて増殖をじゃまする働きを持つ。ただ通常はHIVがつくるタンパク質に逆に分解され、十分な防御力が発揮できないでいる。
研究チームは人の細胞を使った実験で、Aキナーゼの働きでAPOBECが分解されにくい性質に変わることを発見。HIV増殖の勢いを弱める効果を確かめた。
【タンパク質の細胞内品質管理を担う新規還元酵素を発見】
2008年7月25日付 京都大学
永田和宏 再生医科学研究所教授らの研究グループの研究成果が、米国科学誌「サイエンス」誌に掲載されることになりました。
タンパク質の細胞内品質管理を担う新規還元酵素を発見
“ERdj5 is required as a disulfide reductase for degradation of misfolded proteins in the ER.”
Ryo Ushioda, Jun Hoseki, Kazutaka Araki, Gregor Jansen, David Y. Thomas & Kazuhiro Nagata.
[研究成果の概要]
細胞内のタンパク質は、合成されるだけでは機能を持たず、正しく折り畳まれて(フォールディングされて)構造を獲得し、そこで初めて機能を獲得する。遺伝的変異や細胞にかかる種々のストレスによって、タンパク質が正しい構造を獲得できないとき、それらはきわめて不安定で、凝集体やアミロイド線維を作りやすい。従来の分子生物学や生化学では、正しくフォールディングしたタンパク質にしか注意が向けられていなかったが、細胞内には合成直後のポリペプチドから分解されようとしているものまで、さまざまな状態のタンパク質がひしめいていることが明らかになってきた。
細胞内にタンパク質の凝集ができると、細胞の生存は危機に瀕することになり、これらがアルツハイマー病やハンチントン病、パーキンソン病やBSE(プリオン病)など、さまざまのフォールディング異常病の原因となる。
このような事態を回避するため、それぞれの細胞は品質管理機構を備えている。品質管理機構は小胞体におけるものがもっともよく調べられているが、そこではミスフォールドしたタンパク質が生じた場合、主として4つの品質管理機構が作動する。第一の手段は生産ラインの一時停止(翻訳ストップ)、第二は不良品の修理のためのタンパク質(分子シャペロン)の誘導、第三は修理できない不良品の廃棄処分(小胞体関連分解)、そして最後の手段として工場閉鎖(アポトーシスによる細胞死)がある(詳しくは、今月出版された「タンパク質の一生」永田和宏著、岩波新書参照)。
私たちは以前にミスフォールドしたタンパク質の分解処理に関わる新規タンパク質EDEMを発見、報告してきた(EMBO Report, 2001, Science 2003など)。EDEMは分解すべきタンパク質を認識して分解を促進するタンパク質であるが、今回EDEMに会合して、小胞体関連分解に関与する新しいタンパク質ERdj5を発見した。ERdj5はミスフォールドしたタンパク質のジスルフィド結合(S-S結合)を還元(開裂)することができる、小胞体内の初めての還元酵素である。さらにERdj5は小胞体の代表的な分子シャペロンBiPとも結合することを明らかにし、小胞体関連分解にはEDEM/ERdj5/BiPというきわめて重要なタンパク質が複合体を作りながら役割分担をしていることを明らかにし、小胞体におけるタンパク質品質管理のもっとも重要な分解の機構の統合的なスキームを描くことに成功した。
すなわち、ミスフォールドしたタンパク質はEDEMによってまず認識される。ミスフォールドしたタンパク質はジスルフィド結合によって高分子複合体を作ってしまうが、これは小胞体からサイトゾルへの逆輸送に使われるチャネルを通過できない。EDEMに結合したERdj5はこのジスルフィド結合を開裂し、高分子複合体の構造を解くことによって、一本のポリペプチドの状態にunfoldする。一方、ERdj5に結合したBiPはミスフォールドタンパク質をunfoldしたポリペプチド状態に保ったまま逆輸送チャネルにまで運ぶと考えられる。BiPのERdj5への結合はATPの有無によって制御されており、ATPがADPに加水分解されるとERdj5から解離して基質(ミスフォールドタンパク質)をEDEMなどから引き抜いてチャネルへ運ぶ。
EDEM/ERdj5/BiPの3者複合体が小胞体関連分解に関与しているという概念自体がまったく新しく、更に世界的にも発見が待たれていた小胞体内のジスルフィド還元酵素が分解に重要であることを発見したことも大きい。前述のように、タンパク質品質管理機構が破綻することによって多くの神経変性疾患が惹起されるが、本研究はそのような神経変性を初めとするフォールディング異常病の治療戦略にとっても大切な知見を提供すると考えられる。
朝日新聞(7月25日 29面)、京都新聞(7月25日 27面)および読売新聞(7月25日 2面)に掲載。
【虫歯菌溶かす酵素で新事業】
2008年6月9日付 中国新聞
広島大発ベンチャー企業のツーセル(広島市南区)は、虫歯の原因菌(虫歯菌)だけを溶かす新発見の酵素を活用したビジネスに乗り出す。すでに世界10カ国で特許を申請。使用権を家庭用品や食品のメーカーに販売し、歯磨き粉やガムに混入して虫歯予防補助剤としての商品化につなげる。
酵素は、広島大大学院医歯薬学総合研究科の菅井基行教授(細菌学)のグループが2004年、世界で初めて発見した。口内にあるサリバリウス菌などの「善玉菌」を残したまま、ミュータンス菌などの虫歯菌だけを溶かす性質を持つ。菅井教授らは遺伝子情報も解明し、06年にツーセルへ販売・使用権を譲渡した。これまでの研究で、酵素入りの水を与えたラットは通常の水を飲ませたラットに比べ、口内の虫歯菌が激減。20分の1のレベルまで虫歯菌数が減り、完全に死滅したケースも確認したという。
ツーセルは、酵素の使用権を販売して商品化してもらうビジネスモデルを想定し、日本や欧米など10カ国で特許を申請。今年1月、オーストラリアで初の特許を取得した。13年の商品化を目指している。
【アンチエイジングに効く酵素を発見 京大グループ】
2008年3月14日付 産経ニュース
ワインや茶に多く含まれる化学物質「ポリフェノール」の抗酸化作用を強める酵素の遺伝子を、京都大学生存圏研究所の矢崎一史教授(植物分子生物学)らの研究グループが見つけ、14日発表した。動脈硬化などを引き起こす活性酸素の働きを抑える効果があり、新たな抗がん剤の開発などにもつながるとみられている。
研究グループは国内に自生するマメ科の薬用植物のクララを利用。高活性ポリフェノールを多く作る性質があり、遺伝子解析などを行った結果、老化の原因とされる活性酸素を抑える酵素の遺伝子を特定した。
この遺伝子を利用すれば、ポリフェノールの作用を微生物発酵などのバイオテクノロジーで高活性化させた「プレニル化ポリフェノール」を作り出すことが可能になるという。
ポリフェノールは主に植物に含まれる苦みなどの成分で、その一種のカテキンやタンニンは殺菌作用があることが知られる。作用を強めた高活性ポリフェノールは抗腫瘍(しゅよう)や抗炎症、免疫増強、血管増強などの効果があるが、植物から抽出できる量が限られており、これまで利用が進んでいなかった。
研究グループは今後、抗酸化以外の作用を持つ酵素を作る他の遺伝子の特定も目指すといい、矢崎教授は「2例目からは『同じファミリー』の遺伝子を探せばいいので作業は難しくない。抗生物質によらない殺菌剤や美白系化粧品のほか、抗がん作用があるサプリメントや新しい抗がん剤の開発にもつながる」としている。
【ポリフェノールを高機能化するプレニル化遺伝子の発見】
2008年3月14日付 京都大学ニュースリリース
矢崎 一史 生存圏研究所教授らの研究グループは、ポリフェノールの抗腫瘍活性や抗菌活性などの生理活性を飛躍的に高めるプレニル化酵素の遺伝子を世界で初めて見いだすことに成功しました。これにより、将来的には安定な量のプレニル化ポリフェノールの供給が可能になると見込まれます
この研究成果は、米国の「プラント・フィジオロジー(Plant Physiology)」 3月号に掲載されます。
1.概要
植物ポリフェノールは、ワインやお茶等に多く含まれ、抗酸化作用、抗菌作用を持つことから、身体に良いと一般的に認識が広まっている。しかし、もっと活性の強いポリフェノール類が薬用植物で多く見いだされており、それらにはプレニル基と言う「ヒゲ」のような修飾を受けたものが多い。プレニル基とは炭素数5個からなる構造単位の総称で、炭素数5のものをジメチルアリル基、10のものをゲラニル基等と呼び、これが例えば40までつながったものがカロチノイドである。
ポリフェノールにこのプレニル基の「ヒゲ」がつくと、元々のポリフェノールでは非常に弱かった活性が、飛躍的に強くなることが昔から経験的に知られていた。その様々な活性には、 抗腫瘍活性、抗菌活性、抗ウイルス活性、抗酸化活性等の他に、女性ホルモン様活性、免疫増強活性、抗炎症活性、血管増強活性があり、その活性のバラエティーは極めて多岐に及ぶ。その多様性は、プレニル基のつく位置や長さ、また母核化合物の違いにより生まれる。このような化合物は生薬学、薬用植物学の分野ではよく研究され、おおまかに千種類を超す化合物がこれまで生理活性成分として研究されてきた。例えば、健康食品のプロポリスの活性本体もプレニル化ポリフェノールである。
しかしながら、これら天然医薬品であるプレニル化ポリフェノールを植物内で作る酵素、即ちポリフェノールにプレニル基を付加する酵素遺伝子は、30年に及ぶ長い研究にも関わらず、これまで全く未知とされてきた。それを、今回我々の研究室において世界で初めて見いだすことに成功した。
※続きはこちら
【骨壊す細胞つくる酵素発見/粗しょう症の治療に道】
2008年03月7日付 47NEWS
体内で過剰になると、骨粗しょう症や関節リウマチを起こす「破骨細胞」をつくる酵素を、高柳広・東京医科歯科大教授(骨免疫学)らのチームが発見、7日付の米医学誌セルに発表した。人でこの酵素の働きを抑える物質が開発できれば、これらの病気の治療薬につながる可能性があるという。 破骨細胞は骨を吸収する役割をしており、骨をつくる骨芽細胞とバランスよく働くことで正常な骨を保っている。 研究チームは破骨細胞で働いている遺伝子を網羅的に解析。「Btk」と「Tec」という2つの酵素をつくる遺伝子の働きが高まっていることを見つけた。 遺伝子を欠いたマウスを作製したところ、破骨細胞がつくられず、骨がすき間なく埋まり強度が低下する「大理石骨病」を発症。研究チームは、2つの酵素が破骨細胞を形成する役割をしていると判断した。 2つの酵素の働きを抑える薬剤を、関節リウマチや骨粗しょう症を発症させたマウスに投与したところ、症状が改善したという。
【医学系 清水教授ら 脂質非対称にする酵素発見 生命誕生の手掛かりに】
2008年03月04日付 東京大学新聞
清水孝雄教授(医学系研究科)らは、細胞などの内外を隔てる生体膜の脂質を非対称にする酵素と遺伝子群を発見した。生体膜が形成される過程を解明することで、生命誕生の起源を探る手掛かりとなる。研究成果は、1月のキーストン国際会議で発表され、2月20日付の『米国科学アカデミー紀要』(電子版)に掲載された。
【フェノール性脂質の生合成に関わる新規な脂肪酸合成酵素の発見】
2008年01月16日付 東京大学 農学生命科学研究科プレスリリース
[発表概要]
窒素固定細菌Azotobacter vinelandiiの休眠細胞の膜形成に必須であるフェノール性長鎖脂質の生合成に、新規な脂肪酸合成酵素が関わっていることを明らかにした。この脂肪酸合成酵素は、生産物である脂肪酸をポリケタイド合成酵素に直接受け渡すという他の脂肪酸合成酵素とは異なった機能を持っていた。
[発表内容]
以前、醗酵学研究室では、窒素固定細菌Azotobacter vinelandiiの休眠細胞の膜形成に必須なフェノール性長鎖脂質の生合成に、ポリケタイド合成酵素 (PKS) が関わっていることを見出していた[N. Funa, H. Ozawa, A. Hirata and S. Horinouchi. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 6356-6361 (2006)]が、詳細な生合成経路は明らかになっていなかった。A. vinelandiiのゲノム上配列において、このPKSの隣に、I型脂肪酸合成酵素 (FAS) であるArsADが存在していた。ArsADは、既知のI型FASとは異なるドメイン構造をとっており、また、生産物である脂肪酸を放出するドメインを持たないことから、新規なI型FASであると考えられた。
今回、我々はこのArsADの機能解析を行い、フェノール性長鎖脂質の生合成経路の全貌を明らかにした。ArsADは、malonyl-CoAを基質として長鎖脂肪酸を合成し、その後長鎖脂肪酸を放出することなく、そのままPKSに受け渡し、その結果フェノール性長鎖脂質が生成する (図参照)。
通常、FASにより合成された脂肪酸は、放出され、エネルギー代謝など様々な用途で用いられる。しかし、ArsADは生体膜脂質の合成に特化したFASであるため、このようにPKSに受け渡す機構へと進化したのだろう。このArsADと相同性を持つ遺伝子は他の細菌にも存在しており、このような受け渡しの機構は他にも存在している可能性がある。
今回の成果により、脂肪酸合成反応、ポリケタイド合成反応において、いくつかの興味深い知見が得られた。
【異常プリオン分解 「最強」の酵素発見 九産大の満生准教授 BSEなど治療薬への応用期待】
2008年01月12日付 西日本新聞夕刊
牛海綿状脳症(BSE)などの原因物質とされる異常プリオンタンパク質を短時間で分解する酵素を、九州産業大工学部(福岡市東区)の満生慎二准教授(41)=応用微生物学=が見つけた。異常プリオン分解の研究は国内外で進められているが、低温、短時間で作用する酵素の発見はBSEや人のクロイツフェルト・ヤコブ病の治療薬などへの応用が期待され、海外の研究機関からも問い合わせがきている。
満生准教授は、衛生陶器メーカーに勤務していた1990年代、民家の浴場などから約4千種のカビを採取し、人の表皮や毛髪に含まれるケラチンなど分解困難なタンパク質を餌にする好アルカリ性放線菌を発見。九産大に移った後、異常プリオンの分解に応用した。
大学では、発症したハムスターの脳のプリオンを入れた溶液にこの菌が作る酵素を加え、温度や時間を変えながら実験。60度で最も活性化し、3分で異常プリオンを完全に分解したという。
満生准教授は同様の研究を5件、確認している。このうちオランダのグループが115度で40分間、英国のグループが60度、30分以上で完全分解することに成功しているが、満生准教授が見つけた酵素の分解力はそれらを大幅にしのぎ、「ナパーゼ」と命名した。
ただ、正常なタンパク質も分解してしまうため、そのままでは治療薬として使えない。今後、異常プリオンだけに作用する特異性を持たせる必要があり、既に、そうした研究のために米国の大学からナパーゼの送付要請がきているという。満生准教授は「治療薬への応用には遺伝子情報を組み換えて変異させなければならない。簡単ではないが、有用な酵素になるよう実験を重ねたい」と話している。
【神経細胞のシナプス間情報伝達制御リン酸化酵素発見】
2007年12月31日付 知財情報局
-神経変性疾患治療につながる可能性/富山大大塚氏ら-
脳・神経系の適切な情報伝達を支えているタンパク質が新たに発見された。リン酸化酵素のSADキナーゼが神経細胞同士のつなぎ目にあたるシナプスで、他のタンパク質を制御して神経伝達物質の分泌を調節していた。この酵素の破綻はてんかん、統合失調症のほか、アルツハイマー病などの神経変性疾患につながっている可能性もある。富山大学大学院医学薬学研究部の大塚稔助教授、西条寿夫教授らの成果で11月20日、米学術誌『ニューロン』に掲載された。
この成果は大塚助教授らと、カン研究所、三菱化学生命科学研究所、自然科学研究機構、大阪大学との共同研究で、成熟神経細胞間の情報伝達プロセスで神経伝達物質を分泌する側の前シナプスを分子レベルで解析した。成熟したほ乳類の神経細胞を使って実験を進めた結果、神経伝達物質の分泌場所のアクティブ・ゾーンで局所的に発現するSADキナーゼを見つけた。
さらに、従来から神経伝達物質の分泌に直接関わることが知られたタンパク質をリン酸化して活性化させることも分かった。SADキナーゼは、数ある神経突起の中から一本の長い軸索を伸ばすなど、発生期の正確な神経回路網形成に欠かせない分子で知られたが、これにより成熟した神経細胞での機能を示したほか、リン酸化プロセスが脳・神経系の情報伝達機構で重要な役割を担うという、世界で初めての提案になった。
シナプス間の神経伝達物質制御の破綻は、過剰に働けばてんかん、統合失調症などが、抑制的に働けばアルツハイマー病、パーキンソン病などの神経変性疾患につながることが知られ、大塚助教授らの提案が支持されれば、SADキナーゼを新たな標的にした機能解析が進むと期待される。
なお、この研究は科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業CRESTタイプの研究課題「情動発達とその障害発症機構の解明」の支援を受けて進められたものである。
【脳にしかない酵素を発見!
-糖タンパク質の解明を通じて脳が出来上がるまでの過程に迫る-】
京都産業大学 工学部・生物工学科 黒坂 光教授
私たち生物の体を形作り、かつ生体が正常な機能を続けていくのに欠かせない物質であるタンパク質。細胞の中では、遺伝子DNAに書き込まれている遺伝情報が、DNAとよく似た分子であるRNAに転写されます。そのRNAに写し取られた情報が、あたかも翻訳されるかのように、アミノ酸が数珠つなぎにされて、性質の全く異なる分子であるタンパク質が合成されます。しかしタンパク質が機能するにはアミノ酸を連結するだけでは不十分です。タンパク質は、アミノ酸の鎖が正しく折りたたまれ、さらに特定のアミノ酸が化学反応により修飾をうけて(翻訳後修飾)はじめて、機能を持つことができるようになります。この修飾反応の代表的なものに、タンパク質の特定のアミノ酸への糖の結合反応があります。通常、糖は一つだけでなく、糖がいくつも鎖状に連結したもの(糖鎖)がタンパク質に結合しています。このような糖鎖を含む分子を糖タンパク質と呼びます。
糖タンパク質には様々な機能があります。細胞の表面にある糖タンパク質は、その分子上の糖鎖が目印になって、他の分子や細胞が結合することが知られています。白血球が炎症部位の血管内皮細胞に結合したり、精子が卵子を認識するのも糖鎖が関係しています。また唾液などの粘液には糖鎖を多く含むタンパク質が存在します。これらのタンパク質では糖鎖が分子に粘性を与えることが知られています。細胞の表面に粘性を与えるのもこのタンパク質の大切な役割なのです。
ではタンパク質にどのようにして糖が結合するのでしょうか。細胞の中には、糖を順次結合させていくたくさんの酵素が存在します。私たちはこれらのたくさんの酵素の中でも、タンパク質の特定のアミノ酸に、最初に糖を結びつける反応を行うN−アセチルガラクサミン転移酵素と呼ばれる酵素に注目しました。タンパク質上の糖鎖の合成では、まずこの酵素の働きによって特定のアミノ酸の上に一つ糖が付加します。次にその他の多くの酵素の共同作業により、その上に一つずつ糖が付け加えられて、複雑な構造をもった糖鎖ができあがります。したがって、私たちの注目した糖鎖合成の最初のステップを請け負っている酵素は、このようなタンパク質分子上のどの位置に糖鎖を付加するのかを決める重要な酵素であることがわかります。研究を始めた当初、タンパク質に直接糖を結合させるこのような酵素は、一つしかないと考えられていましたが、現在ではそれぞれ性質の異なる20数種類の酵素があると考えられています。私たちが最近発見することに成功したのは、これらの酵素の中で脳にしかないT9、T16という2種類の酵素です。
※続きはこちら
【ヒト糖たんぱく質を合成 横浜市大チーム 薬効の安定に道筋】
2007年12月22日付 朝日新聞
ヒトの糖タンパク質を化学合成する技術を、横浜市立大の梶原康宏教授(合成化学)らの研究チームが開発した。18日付の米化学会誌(電子版)に発表した。貧血や肝炎などの治療薬の薬効を安定させるのに役立ちそうだという。
糖たんぱく質は、貧血治療薬エリスロポエチンや肝炎治療用インターフェロン製剤などに使われている。ただ、動物細胞を利用して製造するので構造を均一にしにくく、医薬品として大量生産する際は品質を一定に保つのに苦労する。
梶原さんらは04年、鶏卵に含まれるヒト型の糖鎖を酵素で切断し、糖鎖を持つプチペドを合成する技術を開発。今回、その技術を使い、76個のアミノ酸からなるヒトの糖たんぱく質ケモカインを合成した。エリスロポエチンやインターフェロンにも活用できそうで、大塚化学と共同で実用化の研究を始めた。
構造が不均一な糖たんぱく質が人体にどんな影響を及ぼすかは不明。化学合成で品質が安定すれば、不安を解消できると期待されている。(服部尚)
【抗がん作用持つ酵素 九大院教授ら発見 正常細胞に副作用なし】
2007年11月08日付 西日本新聞夕刊
九州大大学院歯学研究院の山本健二教授(薬理学)らの研究グループが、カテプシンEと呼ばれるタンパク質分解酵素にがん細胞の増殖・転移を抑える機能があることを発見した。正常な細胞にはまったく影響せず、がん細胞だけを自発的な死(アポトーシス)に導く特性があり、副作用のない抗がん剤など新たながん治療法の開発が期待されるという。15日付の米国がん学会誌(電子版)に論文を発表する。
山本教授によると、カテプシンEはリンパ球をはじめ免疫系細胞などに多く見られる酵素で、生体防御機能とつながりがあるとみられてきた。ただ、具体的な役割は解明されていなかった。
山本教授らはヒトの前立腺がん細胞を使った試験管実験で、カテプシンEを投与すれば正常な細胞は壊れず、がん細胞だけがアポトーシスに誘導されることを発見した。
また、遺伝子操作でカテプシンEを欠損させたマウスと、反対に過剰発現させたマウス、通常のマウスの3種類にヒトのがん細胞を移植した実験では、カテプシンEを過剰発現させたマウスの生存率が最も高く、がん細胞の増殖や転移も明らかに少ないことが分かった。カテプシンEを過剰発現させても健康上の問題は見つからなかった。
これらを解析した結果、カテプシンEにはアポトーシスを誘導する分子「TRAIL」に作用してがん細胞を死に導くだけでなく、異物を除去する細胞「マクロファージ」を活性化し、がん細胞を攻撃させる働きがあることを突き止めた。
従来の抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞まで破壊してしまうものが多く、「有効性と毒性が比例するため、効果の強い薬剤ほど副作用も大きい」(山本教授)悩みがあった。
研究グループは、医薬品開発を進めている。山本教授は「カテプシンEの直接投与や、その発現を増やす薬剤ができるようになれば、副作用の少ないがん治療薬の開発につながるのではないか」と話している。
【ニキビ酵素を抑制 植物エキスを資生堂が発見】
2007年8月30日8時35分配信 フジサンケイ ビジネスアイ
資生堂は29日、ヒマラヤに自生するユキノシタ科の植物「フユベゴニア」のエキスが、ニキビをつくる酵素を抑制する働きを持つことを発見したと発表した。来年以降、薬用化粧品として商品化を目指す。
ニキビは、発生させる「リバーゼ」、色素を沈着させ黒ずませる「チロシナーゼ」、皮膚にダメージを与え、くぼみなどのニキビ跡をつくる「エラスターゼ」の3種の酵素が発生し、進行する。フユベゴニアエキスは、この3種の酵素すべてに対し、抑制作用があることをつき止めた。
【善玉菌の酵素反応 新種のフコース分解酵素】
2007年8月2日 大学共同利用機関法人 News@KEK
昨今の健康ブームを背景に、「腸内環境」とか「善玉菌」、「悪玉菌」などといった言葉もテレビコマーシャル等でお馴染みのものになりました。私たちの腸の中には様々な種類の細菌が混在しています。その中でビフィズス菌は「善玉菌」として、私たちの腸の働きを助けてくれています。ビフィズス菌は、母乳を飲んでいる赤ちゃんの腸の中では圧倒的に数が多い細菌で、大人になるとだんだん数が減ってきます。ビフィズス菌はたくさんの酵素を持っていて、私たちの腸内の物質を分解しています。今日のニュースの主役であるフコース分解酵素(フコシダーゼ)もそのような酵素です。フコシダーゼはどのようなしくみで糖を分解しているのでしょう。その小さなハサミの部分がフォトンファクトリーの放射光を用いた研究で明らかになりました。
フコシダーゼは善玉菌を増やす鍵?
フコシダーゼが分解するフコースは糖の種類のひとつで、ミルクなどに豊富に含まれています。ビフィズス菌のフコシダーゼは菌体の表面にあって、腸の中のミルクオリゴ糖などを分解していると考えられています。赤ちゃんの腸内にビフィズス菌が多いのは、この酵素のはたらきで母乳に含まれるオリゴ糖を栄養にしているらしいことがわかり、フコシダーゼは多くの注目を集めるようになりました。この酵素が糖を分解するしくみがわかれば、大人の私たちの腸内にももっとビフィズス菌を増やすことができるかもしれません。また、その逆反応を利用して、より簡単にフコースを生産できるようになる可能性があります。
石川県立大学の片山高嶺(かたやま・たかね)講師と京都大学の山本憲二(やまもと・けんじ)教授らのグループは、ビフィズス菌から新しいフコシダーゼを発見し、AfcAフコシダーゼと名づけました。このAfcAフコシダーゼは2000個ものアミノ酸からできている非常に大きなタンパク質ですが、その中に900個のアミノ酸からなる触媒ドメイン(領域)があります。フコシダーゼの化学反応はこの触媒ドメイン単独でも行われるため、この部分を詳しく調べれば新しい化学反応に関する情報が得られるのではないかと期待されました。
KEKの若槻壮市(わかつき・そういち)教授、加藤龍一(かとう・りゅういち)准教授、長江雅倫(ながえ・まさみち)博士(現・大阪大学蛋白質研究所)と片山講師、山本教授、京都大学大学院生の土屋敦子(つちや・あつこ)さんのグループは、AfcAフコシダーゼの触媒ドメインの結晶化に成功し(図1)、フォトンファクトリーのBL-5A、BL-6A、AR-NW12Aビームライン、および放射光施設SPring-8のBL41XUビームラインを使用して、この酵素のアポ体(何も結合していない状態)、および阻害剤、基質、分解産物の3つの複合体の立体構造を明らかにしました。
「はたらき」が違うのに「かたち」が似ている?
AfcAフコシダーゼ触媒ドメインの全体構造は、図2に示すようにαヘリックス(らせん)からなるヘリカルドメインを中央にして、図に向かって下側と後ろ側にβシートに富む領域が挟みこむような特徴的なかたちをしていました。
糖を分解する酵素についてはこれまでたくさんの研究がなされており、とても多くの酵素タンパク質が発見されてきました。現在ではこれらの酵素はその特徴ごとに100を超えるファミリーに分類されています。AfcAフコシダーゼはこの中でGH95と名付けられたファミリーに分類されています。このフコシダーゼは、このファミリー内で最初に構造が明らかになった酵素でしたので、この構造がこれまでに明らかになっている他のどのようなタンパク質の構造に近いのかを調べました。その結果、ラブレ菌や魚類腸内細菌のホスホリラーゼ(糖を切ってリン酸をつける酵素)とよく似ていることがわかりました。
私たち生物の体は核酸(DNA、RNA)、タンパク質、脂質などといったさまざまな成分が、機械の部品のように精巧に組み合わさってできあがっています。当然、それぞれの部品には「はたらき」があり、それは部品の「かたち」と密接に関わっています。一般にタンパク質は、そのアミノ酸配列が異なると「はたらき」も「かたち」も異なるものです。今回のようにアミノ酸配列も「はたらき」も異なるタンパク質同士が似たような「かたち」をしているのは大変興味深いことです。
反応中のフコシダーゼの構造を捉える
続いて、このタンパク質がどのようにして反応を行うのかを調べるために、フコースに似せて作られた阻害剤との複合体の構造を解析しました。その結果、阻害剤はヘリカルドメインの中央の窪みにすっぽりと収まっていました。阻害剤複合体とアポ体の構造を比較すると、ヘリカルドメインにあるループ構造が構造変化を起こしていて、まるで巾着袋のように、中に基質を取り込むと袋の口が締まるような動きをして、阻害剤を固定していました。
フコースに似せて作った阻害剤は、この酵素中の本来フコースが結合する場所に、同じように結合していることが推測されます。そこで阻害剤の周辺のアミノ酸を別のアミノ酸に変えて酵素活性を測ったところ、2つの酸性アミノ酸(Glu566, Asp766)と2つの中性アミノ酸(Asn421, Asn423)が反応に重要だということがわかりました(図3)。一般に糖を分解する酵素では、2つの酸性のアミノ酸がハサミの刃の役割を果たすのですが、この酵素の場合刃になるアミノ酸のうちの片方(Asp766)が少しずれた位置にあり、本来刃にはならないはずの中性のアミノ酸(Asn421, Asn423)が刃の位置に来ていました。
では本当のところ切断はどのようにして起こっているのでしょうか? この様子を見るためには基質であるフコースとの複合体の構造を解析したいところですが、酵素をそのまま用いると反応が進行してしまいます。そこで活性に大切なアミノ酸Glu566を変異させ、反応が進みにくい酵素をつくりました。この変異体酵素の結晶に短い時間基質を注入することで、反応する直前の基質の状態をとらえることにしました。その構造(図4)は、確かに阻害剤との複合体の構造から予想された位置で切断が起こっていることを強く示していました。続いて行った分解産物複合体の解析と組み合わせることでより詳細な反応径路が明らかになり、2つの酸性アミノ酸が2つの中性アミノ酸に働きかけることで反応が進行する珍しい酵素であることがわかりました。
ビフィズス菌のAfcAフコシダーゼは、これまでに知られている他のフコシダーゼとは反応の仕方が異なる新種のタンパク質であることが明らかになりました。この特徴的な酵素のおかげで、ビフィズス菌は「善玉菌」として私たちの腸内に共存できているのかもしれません。また、この酵素の立体構造から逆反応を効率的に行う人工酵素を作成できれば、私達にとって有用なフコースをより安価に生産することができるようになる可能性があります。
この研究成果は、アメリカの科学雑誌Journal of Biological Chemistry誌の2007年6月22日号に掲載されました。
※図の説明に関してはリンク元を参照下さい。
【理研など 脳形成の酵素発見 アルツハイマー治療に期待】
2007年6月6日朝日新聞朝刊
記憶や思考をつかさどる大脳皮質で、神経細胞を移動させて規則正しい層構造を形成するのに欠かせない酵素を、理化学研究所などの研究チームが見つけた。酵素は脳の記憶、学習機能やアルツハイマー病と関連していると考えられ、この酵素が作用するタンパク質を突き止めれば、治療につながると期待される。
ヒトやマウスなど哺乳類の大脳皮質は6層構造になっている。類似した神経細胞が層をつくっており、この層が正常に形成されないと神経回路が正しくつながらない。胎児期に大脳皮質の内側で神経細胞が増殖すると、早くできた細胞から脳の表層近くに移動するため、このような構造になるが、移動の仕組みは分かっていなかった。
研究チームは96年、「Cdk5」という酵素を働かなくしたマウスで、大脳の構造が正常でないことを発見した。今回、この酵素に着目しながら、マウスの生きたままの脳を観察。その結果、Cdk5の機能を低下させた胎児や生後まもないマウスの大脳皮質では、神経細胞の移動が遅くなり、細胞の形も変化せず正常な神経細胞に成長しないことを突き止めた。
研究チームの大島登志男・早稲田大学教授は「Cdk5」の活性化がアルツハイマー病に関連しているという研究もあり、活性化を制御できれば治療薬につながる可能性もある」と話している。英科学誌「ディベロップメント」(15日号)に掲載される。【下桐実雅子】
【キラーT細胞の"教育"に必要不可欠な酵素を発見 免疫疾患の発症機構解明と治療法開発に光】
2007年6月1日科学技術振興機構(JST)
JST(理事長 沖村憲樹)と財団法人東京都医学研究機構(理事長 今村皓一)・東京都臨床医学総合研究所は、胸腺におけるキラーT細胞注1の"教育"に必要不可欠な働きをする新しいたんぱく質分解酵素を発見しました。
未成熟なT細胞は、胸腺と呼ばれる臓器の中で増殖・分化します。その際、有用なT細胞を選択して生存させる"正の選択"と、自己を攻撃する有害なT細胞を排除する"負の選択"の"教育"を受けることにより、さまざまな病原体や腫瘍細胞を攻撃できる多様性を持った「T細胞レパートリー」を形成しますが、レパートリー形成までの詳細な機構は不明でした。
今回の研究では、胸腺に特異的に発現する新しい酵素(「胸腺プロテアソーム」と命名)を発見し、この酵素が自己のたんぱく質を通常とは異なる方法で切断して細胞表面に提示することにより、キラーT細胞の正常なレパートリー形成に必須な役割を果たしていることを明らかにしました。この胸腺プロテアソームの遺伝子を欠損させたマウスは、キラーT細胞がほとんど産生されなくなります。
今回の成果は、自己免疫病や免疫不全病などの免疫疾患の発症メカニズム解明や治療法の開発、そして骨髄移植後のT細胞レパートリーの再構築や新しい癌ワクチン療法の試みなどに新たな視点を与えるものです。
本研究は、JST戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)「情報と細胞機能」研究領域(研究総括:関谷剛男)における研究課題「ユビキチンと分子シャペロンの連携による細胞機能制御機構の解明」(研究者:村田茂穂 東京都臨床医学総合研究所 主席研究員)の一環として行われました。今回の研究成果は、2007年6月1日付(米国東部時間)発行の米国科学雑誌「Science」に掲載されます。
<今後の展開>
?患者数およそ100万人と推定される慢性関節リウマチをはじめ、各種自己免疫疾患や近年増加の一途をたどる喘息、花粉症などのアレルギー疾患は、自己と非自己の識別の異常、すなわち"正の選択"と"負の選択"のバランスの乱れが一因と考えることが可能です。従来、"正の選択"の機構が明らかでなかったことから、"負の選択"の観点からのみ発症メカニズムが研究されてきました。今回の成果により、今後"正の選択"の観点から発症メカニズムを検討することが可能となり、これら疾患の理解が一層進展することが期待できます。
?通常、T細胞の分化・成熟は幼少期に完了し、成人では胸腺は著しく退縮します。一方臨床の現場では、癌治療の一環として、あるいは難治性自己免疫疾患の治療法として骨髄移植が頻繁に実施されています。胸腺におけるT細胞教育機構の一層の解明、および成人における胸腺上皮細胞機能を解析することにより、これらの治療をより効率的、効果的なものへ発展させることが期待できます。
?キラーT細胞の主要な役割は、ウイルス感染細胞や悪性化した細胞を排除する抗ウイルス・抗癌作用です。これを利用して癌細胞特異的なキラーT細胞を生体内に投与する癌ワクチン療法が近年注目を浴びています。T細胞の教育機構の解明により、より効果的な癌ワクチン(T細胞教育ワクチン)の開発が期待できます。
【肌のうるおい守るバリアー酵素、ベルギーの大学が解明】
2007年5月28日16時3分配信 asahi.com
皮膚のうるおいを保ち紫外線からのダメージを防ぐ働きがある酵素を、ベルギー・ヘント大のチームがマウスの実験で突き止めた。この酵素は人間にもある。皮膚が乾燥、うろこのようになる魚鱗癬(ぎょりんせん)や、アトピー性皮膚炎などの治療につながる成果として注目される。英科学誌ネイチャー・セルバイオロジー電子版に発表された。
この酵素はカスパーゼ14と呼ばれる。存在は知られていたが、生体内の働きは不明だった。
チームは、この酵素ができないマウスを作ってみた。どのマウスも、きめが粗い異常な皮膚になった。皮膚から逃げる水分の量も増え、保湿機能も落ち、紫外線による損傷が大きくなっていた。
表皮の細胞を培養して調べると、それ自体は紫外線に対する反応が変わらなかったため、細胞を守る「角層」の保護機能に問題があることがわかった。カスパーゼ14は、この角層の働きをコントロールしており、この酵素が働かなくなることで、紫外線を防げなくなったり、皮膚のうるおいを保てなくなったりするようだ。
三重大の水谷仁教授(皮膚医学)は「アトピー性皮膚炎では、乾燥肌が問題になっているが、アトピーのほか、皮膚がんや乾燥肌などの治療法解明につながる成果」と話している。
【炎症反応止める酵素発見 理化学研究所】
2007年04月30日2:19配信 共同通信
本来は異物の侵入から体を守る免疫機構の1つなのに、過剰に起こるとアレルギー疾患やリウマチなどの自己免疫疾患につながる炎症反応を、正常に終わらせる働きを持つ酵素を理化学研究所などがマウスで発見、29日付の米科学誌ネイチャーイムノロジー電子版に発表した。
この酵素の働きを制御できれば、アレルギーなどの治療につながる可能性があるという。
研究チームは、樹状細胞と呼ばれる白血球の一種が細菌やウイルスへの感染を感知すると、同細胞内でタンパク質「NFκB」が炎症反応を起こす遺伝子の働きを高めることに着目。NFκBの働きが低下した細胞を調べ、ある特定の酵素がNFκBを分解する反応を促進していることを突き止めた。
【血液をO型に変える酵素、ハーバード大などが開発】
2007年4月2日3時9分配信 読売新聞
AとB、AB型の赤血球をO型の赤血球に変えることのできる酵素を米ハーバード大などの国際研究チームが開発した。
米国の専門誌ネイチャー・バイオテクノロジー(電子版)に1日発表する。O型の血液は、どの血液型の患者にも輸血できるため、実用化すれば、輸血用血液の血液型の偏りを解消できる可能性がある。
赤血球の表面は、毛のような糖鎖で覆われている。その糖鎖の先に結合している糖の種類によって、A、B、AB型に分かれ、何もついていないのがO型。結合している糖の種類が違うと輸血時に拒否反応が起きるため、O型以外の赤血球は輸血対象が限られる。緊急時など患者の血液型が不明な時はO型を使う。
【アルツハイマー 発症抑制酵素を発見 大阪の研究所 根治療薬開発に光】
2007年3月27日産経新聞
大阪バイオサイエンス研究所の裏出良博研究部長と大阪大学大学院生の兼清貴久さんの研究グループは、認知症のアルツハイマー病を発症段階で抑えるタンパク質(酵素)が脳脊髄(せきずい)液に含まれていることを見つけ26日、米国科学アカデミー紀要に発表した。この病気の治療法はいまだ確立されておらず、発症予測の方法や治療薬の開発に役立ちそうだ。
アルツハイマー病は、今では早期発見し、症状の進行を遅らせることができるが、根治させる治療薬の開発が待たれている。
この病気は脳内でつくられるアミロイド・ベータという小さなタンパク質が神経細胞の周囲に取り付き、細胞を死滅させることが原因のひとつ。裏出部長らは、脳脊髄液の主要なタンパク質であるリポカリン型プロスタグランジンD合成酵素が、アミロイド・ベータと固く結合し、凝集を抑えることを発見。
この酵素を作る遺伝子を欠いたマウスと正常のマウスで比較したところ、脳内にアミロイド・ベータを加えると、遺伝子を欠いたマウスでは3倍以上も凝集した。逆に、この酵素を遺伝的に多量につくるマウスでは数分の1に減った。さらに、ヒトの脳脊髄液からこの酵素を除くと、凝集を抑制する効果が半減した。
【がん細胞を自滅させる酵素を発見 東京医科歯科大チーム】
2007年3月9日3時2分配信 毎日新聞
がん細胞を自滅に導く酵素を、吉田清嗣・東京医科歯科大助教授(分子腫瘍(しゅよう)学)らの研究チームが発見し、9日付の米科学誌「モレキュラーセル」に発表した。酵素の働きを高められれば、抗がん剤の投与量を減らして副作用を軽減する効果が期待できるという。
遺伝子の本体であるDNAが紫外線や放射線などの影響で変異することで、細胞はがん化する。変異が大きいと、細胞中のp53遺伝子が働き、細胞はアポトーシスと呼ばれる自滅現象を起こす。
p53は酵素の働きで活性化すると考えられていたが、その酵素が何かは特定されていなかった。
研究チームは、ヒトのがん細胞を使い、p53が活性化する時にDYRK2という酵素が働いていることを突き止めた。
さらに、薬剤で細胞のDNAを傷つけると、この酵素が細胞質から核の中に移動してアポトーシスが始まることを確認。酵素が働かないようにすると、アポトーシスが起きなくなることから、p53にスイッチを入れる働きを持つと断定した。
吉田助教授は「抗がん剤や放射線治療は正常な細胞にもダメージを与える。DYRK2が必要な時に必要な細胞で働くよう工夫できれば、患者の負担を小さくする治療につながる」と話す。【田中泰義】
【植物のフラボノイドの構造を決定する酵素を発見】
- 植物の抗酸化成分を活用する健康機能増強に期待 -
2007年2月22日 独立行政法人 理化学研究所プレスリリース
◇ポイント◇
・植物体のフラボノイドパターンを決定する配糖化酵素UGT89C1を発見
・バイオインフォマティクスによって効率的に目的遺伝子を探索
・植物フラボノイドを人為的に改変することにより健康増進の機能向上に期待
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、植物の主要な抗酸化物質であるフラボノイド群の最終的な構造(フラボノイド成分パターン)を決定する酵素遺伝子を発見しました。これは、理研植物科学研究センター(篠崎一雄センター長)代謝機能研究チームの榊原圭子研究員、メタボローム解析チームの峠隆之リサーチアソシエイトおよび両研究チームリーダーでもある斉藤和季グループディレクターらによる研究成果です。
フラボノイドは、活性酸素の除去、抗がん作用、高血圧の改善、抗アレルギー作用などの健康増進機能をもつポリフェノールの一種です。花や果実の色素成分であるアントシアニン、ダイズに含まれるイソフラボン、そばのルチン(フラボノール)等が一般的によく知られています。植物中でフラボノイドが安定に蓄積するためには、配糖化酵素によってフラボノイドの骨格に糖を付加することが必要です。糖付加に関与する一部の遺伝子は既に見つかっていますが、比較的ゲノムサイズの小さいシロイヌナズナでさえ、配糖化酵素は107種類もあり、正確な機能をもつ遺伝子を探すのは困難でした。
今回の研究では、遺伝子共発現解析※1というバイオインフォマティクス手法を用い、シロイヌナズナのフラボノイド成分パターン決定に最も大きく関わっている配糖化酵素※2(UGT)遺伝子を効率的に選定しました。その結果、最も可能性の高いUGT89C1遺伝子を見つけ、この遺伝子が発現しなくなった変異株ではフラボノイドの一つであるフラボノールのうち、7位にラムノース(自然界に存在する糖の一種)を付加したフラボノールが欠損し、野生株には存在しない新規のフラボノール化合物が蓄積していたことがわかりました。すなわち、今回同定した遺伝子から発現する酵素は、植物のフラボノイド成分パターンを決定する重要な酵素であると言えます。
今後、さらに多くの種類のフラボノイド配糖化酵素が見つかれば、フラボノイドの人為的な改変が可能になり、植物フラボノイドによる健康増進機能向上の可能性が期待できます。
本研究成果は、米国の科学雑誌『Journal of Biological Chemistry』2月22日のオンラインにプレビュー版が掲載されました。
背 景
フラボノイドは、活性酸素の除去、抗がん作用、高血圧の改善、抗菌・抗ウイルス作用、抗アレルギー作用などの健康増進機能をもつポリフェノールの一種です。古くから、人類は、フラボノイドを含む植物の葉や果実を民間薬として利用してきました。花や果実の色素成分であるアントシアニンをはじめダイズに含まれるイソフラボン、そばのルチンもフラボノイドの仲間で、現在までに6,000種類以上のフラボノイドの構造が明らかにされています。
フラボノイドは(一部の例外を除いて)グルコース、ラムノース、キシロースなどさまざまな糖を付加することによって植物体に蓄積することができます。言い換えれば糖を付加できないと植物はフラボノイドを生産する能力があっても蓄積できません。シロイヌナズナではフラボノイドの構造から少なくとも9種類の糖の付加に関わる配糖化酵素遺伝子(UGT)の存在が示唆されていますが、このうち既に明らかになっているのは4種類だけです。全ゲノム配列が解読されたことでモデル植物であるシロイヌナズナやイネに存在するUGTの遺伝子配列やその存在数は明らかになりました。しかしながら、比較的ゲノムサイズの小さいシロイヌナズナでさえ、UGT遺伝子は100種類以上有ります。またフラボノイドだけでなく他の二次代謝物質も糖付加のターゲットであることから、どのUGT遺伝子がどの物質に関係しているか推定することは困難でした。
※詳細はリンク元を参照下さい。
【ペルオキシソーム酵素を成熟型へ変換させるタンパク質を発見】
- 脂肪酸代謝の分子機構解明、創薬の新たな手がかりに -
2007年1月26日 独立行政法人 理化学研究所 埼玉医科大学プレスリリース
◇ポイント◇
・長年科学者が追い求めてきたペルオキシソームプロセッシング酵素を見出す
・脂肪酸の燃焼(β−酸化)の制御に大きく関わる酵素
・肥満、生活習慣病の分子機構解明と創薬に大きな1歩
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、埼玉医科大学(山内俊雄学長)との共同研究で、ゲノムインフォマティクスから予測した、今までに機能が不明であったタンパク質「Tysnd1(ティワイエスエヌディーワン)」が脂肪酸の代謝に重要な役割を果たす新しい酵素であることを発見しました。これは、理研横浜研究所ゲノム科学総合研究センター(榊佳之センター長)のKurochkin Igor (クロチキン イゴール)研究員、Schoenbach Christian(ショーエンバッハ クリスチャン)元チームリーダーらと埼玉医科大学ゲノム医学研究センター(村松正實所長)の岡崎康司教授らとの共同研究の成果です。
脂肪酸の代謝は、細胞内小器官であるペルオキシソーム※1とミトコンドリアで行われ、特にペルオキシソームでは長い鎖長の脂肪酸の代謝を行います。これまでの研究では、このペルオキシソームでの脂肪酸の代謝経路に関わる主要な酵素が「プロセッシング※2」という修飾を受けて成熟し、活性化した形になって機能することが報告されていました。しかしプロセッシングを行う酵素については、国内外の研究者が長年追い求めてきたにも関わらず、これまで発見されていませんでした。
今回の研究では、ゲノムワイド※3な情報解析から、このプロセッシングを行う酵素を予測した後に実験で確認したものです。その結果Tysnd1は、タンパク質を切断するプロテアーゼ活性を持ち、ペルオキシソームにおける脂肪酸燃焼に関わる主要な酵素をすべて切断して成熟させる機能を持つ「ペルオキシソームプロセッシング酵素(PPP)」であることがわかりました。さらに、この酵素は高脂血症治療薬を投与したマウスの肝臓でも増加することが今回の実験で確かめられました。
今回の発見は、脂肪酸代謝に関わる疾患、例えば、肥満、脂肪肝、高脂血症の治療や創薬につながる大きな手がかりとなると考えられます。
本研究成果は、欧州の科学雑誌でネイチャーの姉妹紙である『EMBO Journal』(2月7日号)に掲載され、それに先立ち、オンライン版(1月25日付け)に掲載されます。
【理化学研究所、植物生長ホルモン「ジベレリン」の働きをブロックする新酵素を発見】
2007年1月24日配信マイライフ手帳@ニュース
理化学研究所は、植物生長ホルモンの「ジベレリン」の働きを特異的にブロックする新しいタイプの酵素を発見した。これは、理研植物科学研究センター(篠崎一雄センター長)促進制御研究チームの山口信次郎チームリーダー、生長制御研究チームの神谷勇治チームリーダーらと、ミシガン大学のEran Pichersky(エラン ピチャスキー)教授らの研究グループによる共同研究の成果だと説明する。
ジベレリンは酸性物質で、細胞内ではおもにイオンとして存在すると考えられ、この酸性の性質はジベレリンが植物体内でホルモンとして働くために重要だと指摘。植物のなかには酸をメチル化して中性に変える酵素があるが、今までジベレリンを特異的に中性にする酵素の存在は知られていなかったという。
今回の研究では、モデル植物であるシロイヌナズナのゲノム配列情報をもとに24のメチル転移酵素(他の化合物に対してメチル基(-CH3)を転移する酵素)遺伝子を見出し、これらの中からジベレリンと特異的に反応する2つの酵素GAMT1とGAMT2を発見したという。
大腸菌内で作ったこれらの酵素を調べると、ジベレリンの酸をメチル化してホルモン活性をブロックしたとのこと。この酵素はシロイヌナズナの未熟種子に多く含まれている。この遺伝子を壊した植物は鞘(さや:未熟種子と果実から成る)にジベレリンが蓄積し、この酵素を植物の体中のどこでも作られるように変えた植物は草丈が小さくなったという。
このミニ植物に含まれるジベレリンを最新の微量分析法で調べたところ、正常な植物よりもジベレリン含量がずっと低下していることが分かったと説明。これらの結果から、GAMTは酸をメチル基でブロックする新しいタイプのジベレリンの不活性化酵素で、昨年研究グループが明らかにしたイネのEUI遺伝子とは全く別の機構により生長ホルモンを不活性化することが明らかになったと指摘する。将来、この酵素を用いた新しい植物生長調節技術の開発につながることが期待されるとしている。
【『メラニン色素』の輸送を阻害する新酵素発見】
- 皮膚の暗色化制御を行う分子標的として期待 -
2006年9月14日独立行政法人 理化学研究所 国立大学法人 東北大学プレスリリース
◇ポイント◇
・メラニン色素輸送に必須のタンパク質「Rab27A(ラブエー)」を不活性化する酵素を発見
・多様なRabとその機能を制御する酵素との関係を探る新たな手法を開発
・肌の美白維持に期待
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)と国立大学法人東北大学(吉本高志総長)は共同で、肌や髪を黒くするメラニン色素の輸送を阻害する新しい酵素「Rab27A-GAP(ラブ27エー・ギャップ)」を発見しました。福田独立主幹研究ユニットの伊藤敬基礎科学特別研究員と東北大学大学院生命科学研究科福田光則教授(福田独立主幹研究ユニットユニットリーダー兼務)による研究成果です。
メラニン色素は、「メラノサイト※1」と呼ばれる皮膚の基底層にある細胞の中で合成され、メラノソームと呼ばれる膜に包まれた袋(小胞)に貯蔵されています。このメラノソームが、メラノサイト内を移動し肌や髪の毛を作る細胞に受け渡されることで、肌や髪の毛が黒くなります。メラノサイトにおけるメラノソームの輸送は「Rab27A」と呼ばれる低分子量Gタンパク質※2の活性化が不可欠で、GTP(ジー・ティー・ピー)と結合し活性化したRab27Aが、共に働くパートナーとなるタンパク質と結合することではじめて、正常に行われます。しかし、このRab27Aが活性化したり、逆に不活性化したりする分子メカニズムそのものは、これまで全く解明できていませんでした。
今回、研究グループは、Rab27A分子を特異的に不活性化させる分子の探索を行い、Rab27A不活性化酵素(Rab27A-GAP;Rab27A分子のGTP加水分解活性を促進する酵素)を同定することに初めて成功しました。同定した酵素「Rab27A-GAP」は、試験管内で活性化型の「GTP-Rab27A」から不活性化型の「GDP-Rab27A」への変換を促進するだけでなく、メラノサイトに過剰に発現させるとメラノソーム上のRab27A分子を不活性化し、メラノソームの輸送阻害を引き起こす新機能があることを明らかにしました。
今回同定したRab27A-GAP分子はヒトの皮膚や毛根においても機能している可能性が高く、メラノソーム輸送を人為的に制御するための新規の分子標的として応用可能です。今後、この分子の活性化・不活性化を促す薬の開発が進めば、肌の美白の維持や白髪発生の抑制などの研究にも役立つものと期待されます。
本研究成果は、米国の科学雑誌『The Journal of Biological Chemistry』オンライン版に近く掲載されます。
<今後の展開>
紫外線を浴びると、私達の体内ではメラノサイトが活性化され、合成されたメラニン色素が皮膚に輸送・沈着することにより日焼け、しみ、そばかすが発生します。つまり、メラノサイトにおけるメラニン色素輸送の人為的制御は、肌の美白維持とも密接な関連があると言えます。今回発見したRab27A不活性化酵素(Rab27A-GAP)は培養メラノサイトにも発現しており、ヒトの皮膚や毛根においても機能している可能性が極めて高いことから、皮膚の暗色化制御の分子標的や白髪発生の抑制などに応用可能です。今後、Rab27A-GAPのGAP活性を促進・阻害する薬の開発が進むことが期待されます。
カテゴリーから探す
コンテンツを見る
- ヴェル酵素ネットメッセージ
- 最新酵素ニュース
- 山本家の三種の神器
- 喜びの声
- よくある質問
- 「サプリメントアドバイザーが社会に果たす役割」
- 植物と微生物と共に生きる〜『お母さんの手作り製酵素』〜
- 植物と微生物と共に生きる 〜山本家のくらしの知恵づくり『青じそ・みょうが・生姜』〜
- 家庭で作る季節の薬膳と家庭菜園〜山本家のくらしの知恵づくりメモ『きゅうりが!?』〜
- 植物と微生物と共に生きる 〜山本家のくらしの知恵づくり『スイートフェンネルの花ざかり』〜
- 植物と微生物と共に生きる 〜山本家のくらしの知恵づくり『梅干し出来上がりました』〜
- 会員ページのお知らせ
- 「風の囁き‥」2010年11月14日発行・店長コラム
- 舞道『観音舞』葉月の会
- 植物と微生物と共に生きる 〜山本家のくらしの知恵づくり『スイートバジルが大きく育ちました。』〜
- 秋まき種のプレゼントします。
- なでしこさぷりシリーズ紹介
- 植物と微生物と共に生きる 〜家庭菜園のすすめ(最高の贅沢食材『我がサラダ』)〜
- 植物と微生物と共に生きる 〜山本家のくらしの知恵づくり「もくじ」

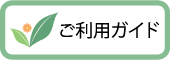
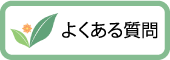
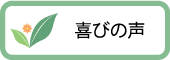
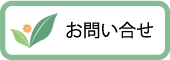




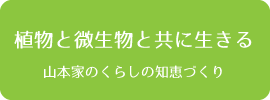

 店長コラム「種。脈々と続いていく。 」
店長コラム「種。脈々と続いていく。 」


















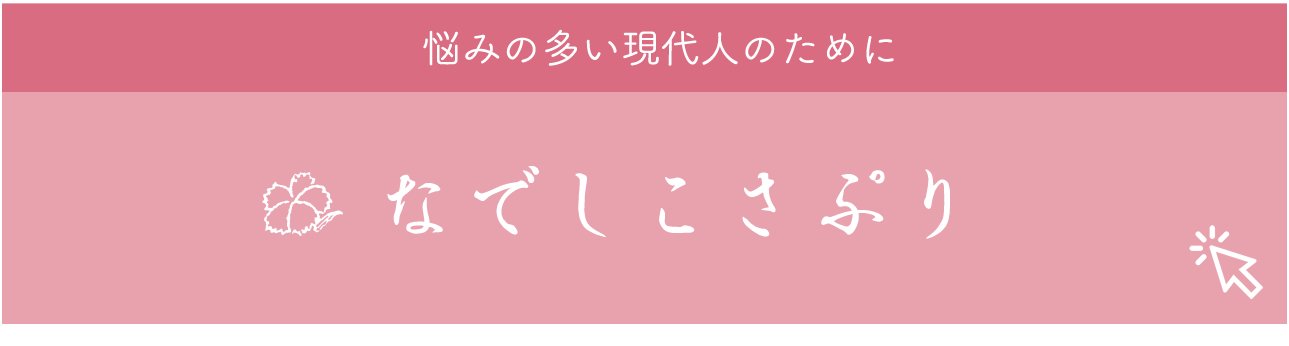
 なでしこさぷり(紅梅)
なでしこさぷり(紅梅) なでしこさぷり(ときわ)
なでしこさぷり(ときわ) なでしこさぷり(桔梗)
なでしこさぷり(桔梗) なでしこさぷり(向日葵)
なでしこさぷり(向日葵) 植物エキス発酵飲料・酵素サプリメント専門店ヴェル酵素ネットは、【flowflow.shop】に生まれ変わります。
植物エキス発酵飲料・酵素サプリメント専門店ヴェル酵素ネットは、【flowflow.shop】に生まれ変わります。


